| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付時間:10:00~17:00 | ● | ● | ● | ━ | ━ | ● | ● | ● |
※定休日:水、木曜日
毎月営業カレンダーにてお知らせします
※受付時間:10:00~17:00
※施術料金:¥6000円(税込)
営業カレンダー・お知らせ

1月の予定です。
1月の休診日は
1/1(木)~1/4(日)
7日(水)、8日(木)、
14日(水)、15日(木)、
21日(水)、22日(木)、
28日(水)、29日(木)、
です。
受付時間は10:00~17:00です。
※お問い合わせ・ご予約は、御電話、メール、LINEで受け付けております。
休日・時間外でもメール・LINEは受け付けております。
(ご返信に少し時間をいただく場合があります。ご了承下さい)
宜しくお願い致します。

2月の予定です。
2月の休診日
4日(水)、5日(木)
11日(水)、12日(木)
18日(水)、19日(木)
25日(水)、26日(木)
です。
受付時間は10:00~17:00です。
※お問い合わせ・ご予約は、御電話、メール、LINEで受け付けております。
休日・時間外でもメール・LINEは受け付けております。
(ご返信に少し時間をいただく場合があります。ご了承下さい)
宜しくお願い致します。
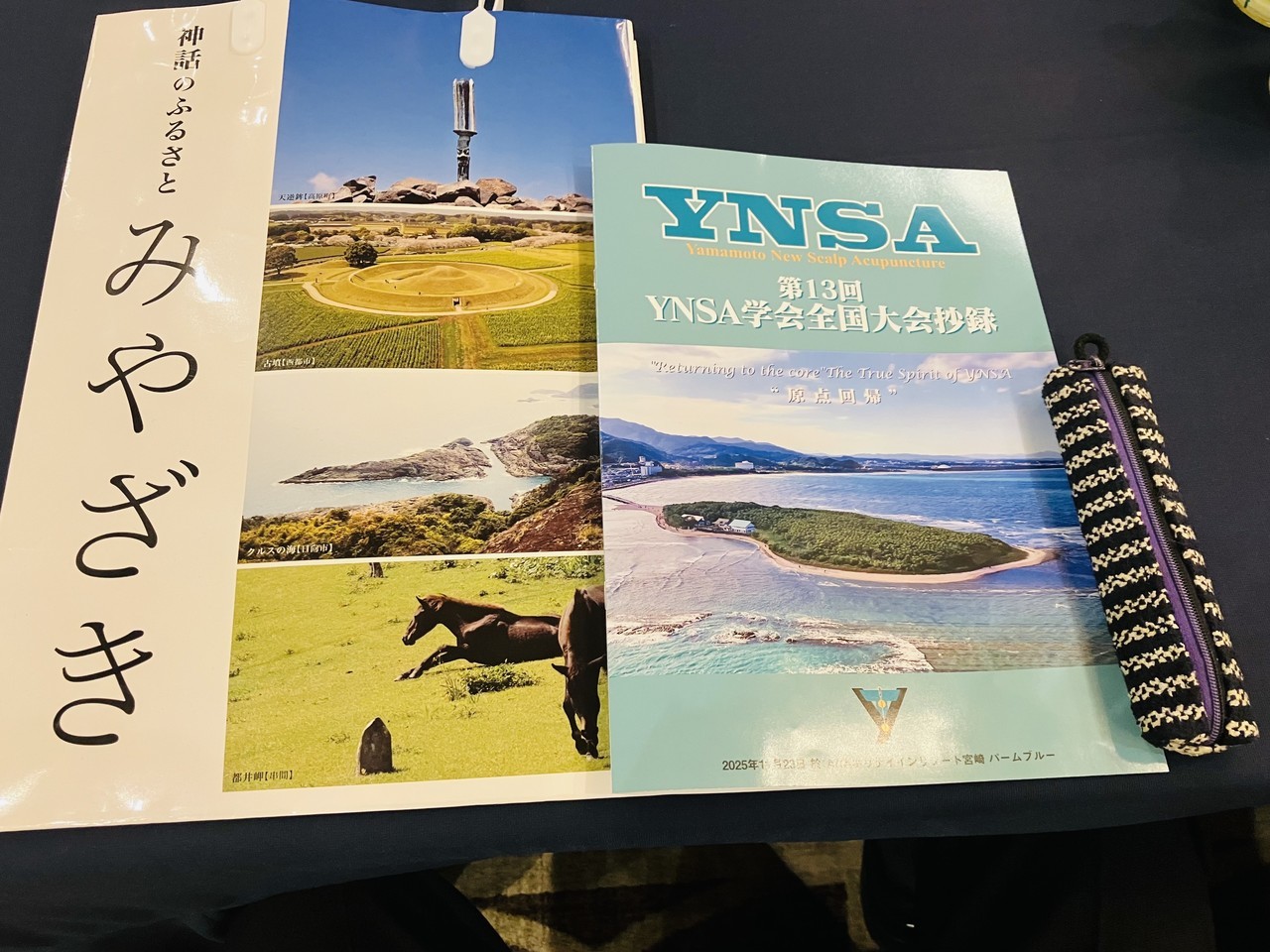


YNSA学会全国大会に参加させていただきました。
宮崎に来るのは、コロナ禍前以来なので約7年ぶりくらいかと。
今回は山元先生の故郷である宮崎での開催でした。
残念ながら山元敏勝先生とお会いすることはできませんでしたが、後継者の山元美智子先生のご家族ならではのエピソードや、山元美智子先生の施術も拝見することができたのは、とても貴重でした。
そのほか先生方の各症例の発表では、難しい疾患でも結果が出ている症例もあり、YNSAの奥深さと可能性を感じる事ができました。
基本的な事の重要性を再認識しました。
ほかに海外でのYNSA事情、医療に取り入れられている状況などの紹介する動画を拝見でき、世界に認められているYNSAを改めて再認識しました。
特に、ドイツでの、脳卒中の患者への救急車内での鍼治療の例には衝撃っをうけました。
懇親会では、懐かしい先生方と意見交換・情報交換が出来て、大変有意義な時間が過ごせました。
会場の近くには、景勝地でパワースポットでもある青島神社・青島海岸・鬼の洗濯岩も観光し、宮崎の自然に癒されリフレッシュできました。
今回は改めて気づいたこともあり、今後の施術にも生かして行きたいと思います。
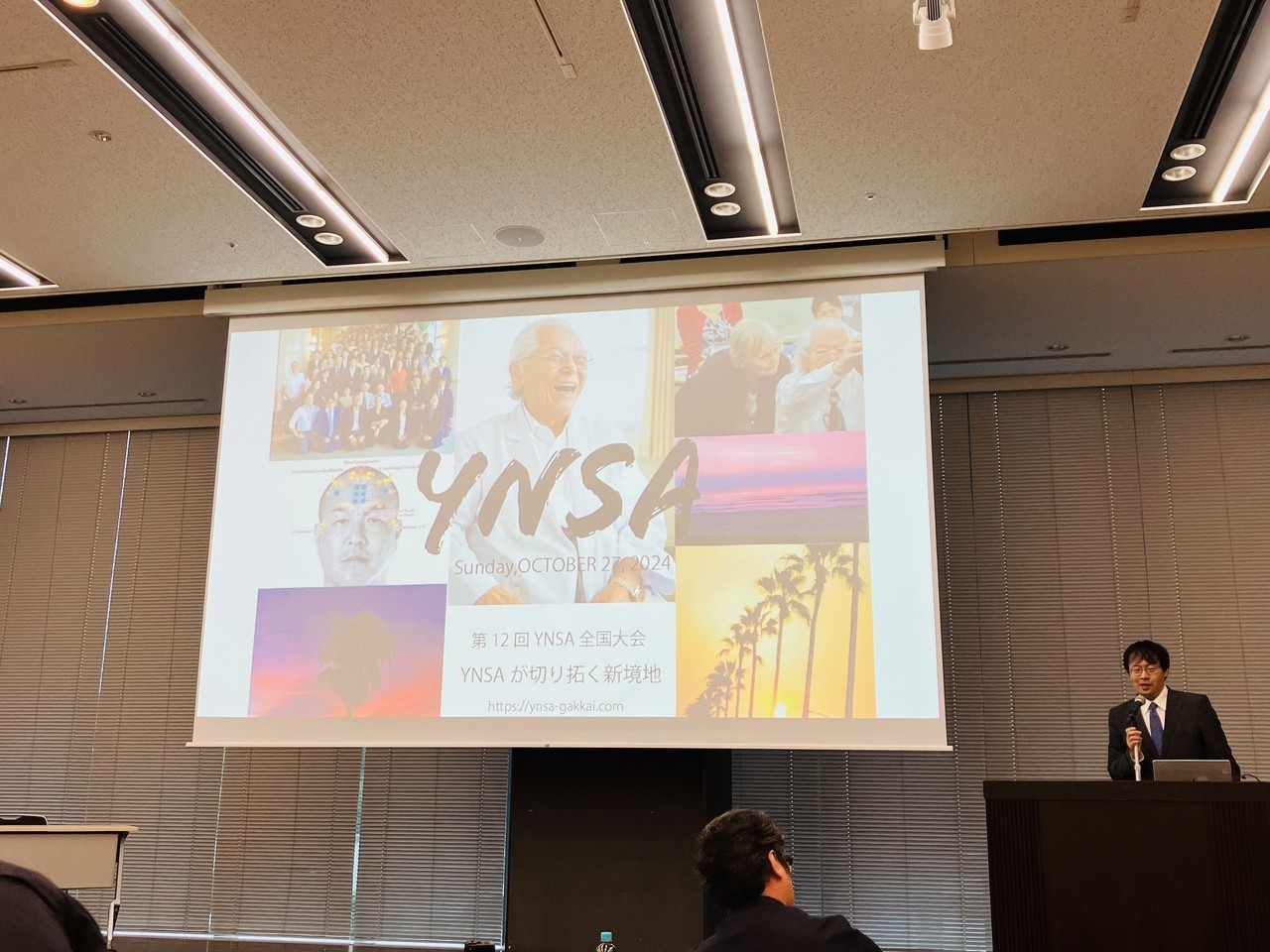
YNSA学会全国大会に参加させていただきました。
2024年10月27日(日)YNSA学会全国大会が東京お茶の水にて開催されました。
数年ぶりにリアル参加させていただきました。
zoom参加とは違い、先生方と直接情報交換・質問・意見交換ができて
大変有意義な時間でした。
学会員による症例発表・大阪大学名誉教授の佐古田三郎先生の基調講演
ドイツで活躍されているドロテア・ツヴァイス=シェス博士の報告
山元敏勝先生の未公開特別映像など大変貴重なお話も伺うことができました。
山元敏勝先生はじめ理事の先生方、スタッフの皆様、お話させていただいた先生方
ありがとうございました。
やはり「直接会って話をする。」
ということは重要だと痛感しました。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>10:00~17:00
※定休日:水、木曜日
ご予約・お問い合わせフォーム
・LINEは24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
つばさ鍼灸院

住所
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町10-11 オラシオン南町401
アクセス
・静岡駅南口から徒歩3分
・当院には駐車場はありません。
お車でお越しの際は、周辺にコイン パーキングがあります。
・自転車用駐輪場はあります。(1台分)
管理用の札を付けるルールです。
自転車でお越しの際は、お知らせください。
受付時間
・10:00~17:00
定休日
・水、木曜日


